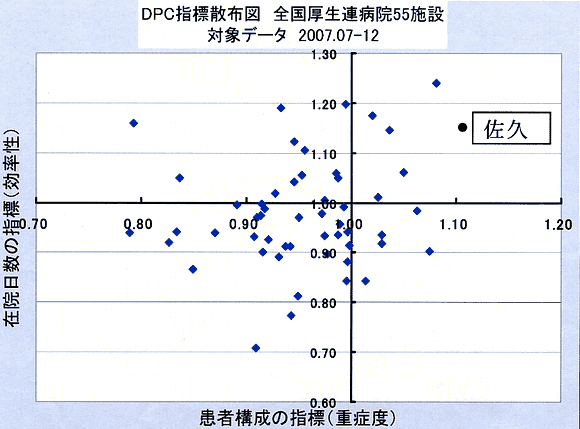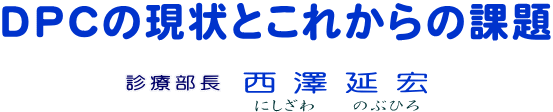
DPCは平成15年に特定機能病院に導入され、当院は平成18年4月から対象病院となって(DPC導入第一報)現在に至っており、既に3年が経過している。この間、全国のDPC対象病院は着実に増加しており、平成21年度に570病院を加えて、現在、全国で約1300病院が参加することとなっている。総じて規模の大きな病院が参加するので、全国で約90万床といわれる一般病床の約半分の45万床程度がDPCで運用されることとなっており、DPCという制度は医療界の中で定着したと言えよう。長野県厚生連でも小諸・篠ノ井・北信・安曇・下伊那・松代の各病院がDPC対象病院となっており、小海分院も本年7月からDPC対象病院になる予定である。  DPCが導入されると、DPCの「ものさし」の面として、自院でのデータ分析だけでなく、他の病院との比較が容易にできることとなる。過日、NHKでも取り上げられたように他の病院との比較を行う中で、自施設の優れた点・問題点の把握が可能になる。「病院の診断が可能になる」と言っても差支えないであろう。当院は総じて、標準化・効率化が進んだ病院であり、どこに出しても恥ずかしくない医療を行っているが、データを分析すると細かい点では改善すべき点もある。我々医療従事者は、少しでもいい医療を患者さんに提供することを願っており、その中で他との比較ができることは改善の第一歩と言え、大きな福音である。また、包括支払制度としてのDPCに関しては、従来の出来高払い制度より増収傾向にあり、DPCを導入した病院は総じて経営が改善してきている。 DPCが導入されると、DPCの「ものさし」の面として、自院でのデータ分析だけでなく、他の病院との比較が容易にできることとなる。過日、NHKでも取り上げられたように他の病院との比較を行う中で、自施設の優れた点・問題点の把握が可能になる。「病院の診断が可能になる」と言っても差支えないであろう。当院は総じて、標準化・効率化が進んだ病院であり、どこに出しても恥ずかしくない医療を行っているが、データを分析すると細かい点では改善すべき点もある。我々医療従事者は、少しでもいい医療を患者さんに提供することを願っており、その中で他との比較ができることは改善の第一歩と言え、大きな福音である。また、包括支払制度としてのDPCに関しては、従来の出来高払い制度より増収傾向にあり、DPCを導入した病院は総じて経営が改善してきている。ただ、その一方、効率化が進む中で、平均在院日数の短縮が起こっている。これは患者さんにとって治療が早く済むという意味では一定望ましいことであるが、十分な療養ができなくなるという負の面もある。現在、地方病院で、病床の稼働率が低下し病棟閉鎖などが行われており、この東信地区でも同様の傾向にある。この現象は、医師・看護師不足という要因とともに、DPC導入によって平均在院日数が短縮したことが大いに影響している。 〈Ⅱ.地方の病院にとってのDPC〉 DPCの制度下では地域医療を支えている地方の病院は経営・運営の両方の面から不利な状況にある。 その要因としては、高齢化、広域性、機能分化困難、連携施設の不足、医師・看護師不足が挙げられている。 1.高齢化 高齢者は、持病である併存疾患を有することが多く、手術後の合併症が生じる可能性も高い。また、回復力が十分でないため、治癒に時間がかかり、在院日数が延長することが多い。つまりDPC環境下では同じ診断であれば、年齢に関係なく診療報酬は同じであるが、高齢者ではコストがかかり、看護必要度も高い。都会に比べて、地方では高齢化が進んでおり、地方における医療ではコスト高になることとなる。 2.広域性 地方の病院では、受診者が広域に渡ることとなる。また、公共交通機関が発達していないこともあり、車の運転ができない場合、通院の手段が乏しい。本来外来で十分治療可能な治療も入院で行わねばならないこともある(乳房温存術の放射線治療など)。また、化学療法や手術前の検査も入院で行わざるをえない場合がある。こういった場合、経済性・効率性などでは明らかに不利になる。 3.機能分化困難 地方の病院では、軽症から重症まであらゆる分野の患者さんを受け入れることとなる。その中には明らかに在院日数が長く収益性の低い疾患もあるが、選択することなく全ての患者の受け入れを行うこととなる。周辺の医療機関が乏しいので、外来患者が多くなり、初診の患者も多くなるので、紹介率は低くなり、地域医療支援病院の取得・入院時医学管理加算などの取得は困難である。また、外来患者が多いことは、医師の労働条件をきつくするため、避けたいところであるが、現状では外来を縮小することは困難である。 4.連携施設不足 地方では開業医が少なく、病院の医師がかかりつけ医機能を有することもある。また、急性期を脱した患者が回復期・慢性期の病院に移ろうにも、そのような病院はあまりない。したがって、地域連携パスは進まず、在院日数の延長が生じる。 5.医師・看護師不足 地方においては、都会に比べて、医師不足・看護師不足が顕著である。そのため、地方の病院の経営は苦しく、給与も十分でないことが多い。また、残っている医師・看護師の労働はきつくなるため、疲弊が進むこととなる。 〈Ⅲ.佐久総合病院の取り組み〉 当院は農村でも都会に負けない医療を行うことを目指し、地方では標準化・効率化が困難であることが多いのを認識した上で、標準化・効率化できる部分は徹底的に行ってきた。そのため、DPCのデータにおいて、効率性・複雑性共に、1を超えているが、これは地方病院としては、稀有である。
佐久総合病院では、平成18年4月からDPC対象病院となったが、DPC導入は医療の質の向上を目指す取り組みと考えて努力をしてきた。特に医療の標準化にむけて行ってきた主な取り組みは下記のようである。 (1)クリニカルパスの充実 DPCにおいて、標準化を進めるために各病棟・外来でのクリニカルパスの充実は必須であるが、当院ではクリニカルパス専任師長を配置し、全病院的にパスの充実を図っている。 (2)通院治療センターの設立 外来化学療法を行う部屋を整備し、専任の看護師・薬剤師を配置して、外来で化学療法を行う患者は一括で管理している。 (3)術前検査センターの設立 (日帰り手術センターの活用)  従来、当院は地方では唯一といわれる日帰り手術センターを有していたが、それに併設させる形で、術前検査センターを設立した。これは手術を控えた患者への説明・検査・薬の管理などを看護師が中心で行うシステムである。このセンター設立は日本で初めての試みであるが、医療界の中でかなり評価が高く、取材・視察が多くなっている。 従来、当院は地方では唯一といわれる日帰り手術センターを有していたが、それに併設させる形で、術前検査センターを設立した。これは手術を控えた患者への説明・検査・薬の管理などを看護師が中心で行うシステムである。このセンター設立は日本で初めての試みであるが、医療界の中でかなり評価が高く、取材・視察が多くなっている。(4)地域連携室の多機能化 地域医療連携室では、本来の紹介患者の受け入れだけでなく、院内の病床管理を行い、後方連携として転院の手助けを行っている。これにより、地域全体の病床に目を配り、地域全体として医療を支えるシステムを構築している。また、地域連携パスの事務局としての活動も行っている。 〈Ⅳ.これからの課題〉 平成22年度には、DPCにおける調整係数がなくなることがはっきりしている。調整係数とは、DPCという包括支払制度に移行する中で、経済的な不利が生じないように、前年と同じ医療を行っていれば前年と同じ収入が担保されるように調整する仕組みである。この係数が高い病院は、総じて高コストの医療を行なっていることとなり、係数がなくなると経営的に  マイナスが大きくなる。当院は幸いにも調整係数の低い方に属する病院であり、廃止のインパクトは小さいと考えている。これは当院が、患者さん第一に、無駄なことは省き、標準的な医療を提供することを心掛けてきた結果であるが、まだ、一部に改善の余地があり、必要な見直しを行なって行きたい。 マイナスが大きくなる。当院は幸いにも調整係数の低い方に属する病院であり、廃止のインパクトは小さいと考えている。これは当院が、患者さん第一に、無駄なことは省き、標準的な医療を提供することを心掛けてきた結果であるが、まだ、一部に改善の余地があり、必要な見直しを行なって行きたい。一方で国は、一定の機能を有する病院に機能評価係数という形で、診療報酬上加算をする考え方を持っており、その議論がDPC評価分科会というところで盛んに行われている。その中で2月12日に地方病院の立場からということで当院からの意見を求められ、小生が意見を述べてきた(詳細は、厚生労働省のHPにあるので参考にしていただきたい)。地方病院にもDPCが拡大している現在、「地方において必要な診療機能を果たして地域医療を守っている病院に対しての加算・評価を是非検討していただきたい」という趣旨の発言をしてきた。 ただ、分科会の委員は、錚々たるメンバーではあるが、大学教授・都会の大病院の院長であり、地方の立場に立つ委員はいない。「へー、本当に地方は大変なんだ」と言ったある委員の言葉が全てである。先行きはかなり厳しいと言わざるをえない。 さまざまな加算の取得には、医師・看護師を十分に集め、機能分化・標準化・効率化を行うことが必要であるが、医療資源の乏しい地方では対応が困難である。そのために、たとえ、DPCに参加しても各種の加算の取得ができない病院が多い。このままでは、地方病院の経営が悪化し、地域医療の衰退が生じるのは自明の理であり、ますます、都会と地方との医療の格差が大きくなってくるであろう。 しかしながら、佐久総合病院はこの地において、地域医療を守り、地域を守っていく使命がある。DPCに対応し、そのデータを利用して、さらなる高い医療の質を目指して絶え間ない努力をしていかなければならない。また、それが再構築へのもっとも重要な課題の一つであると信じている。 また、現在、長野県厚生連では、お互いのDPCデータを見比べることのできるシステムの構築を進めている。これにより、他の厚生連病院と切磋琢磨し、よりよい医療の提供体制を構築し、長野県厚生連全体の医療の標準化を図っていきたいと考えている。
|