農村医学夏季大学
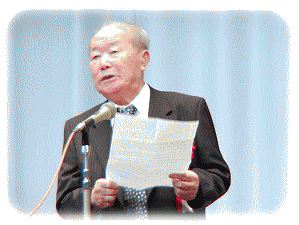
故・若月俊一 名誉総長
農村医学夏季大学講座の歩み
夏の信州山間部の涼しさと静かな環境を利用して、市民大学的なものを開催してみようという、いわゆる「夏季大学」的発想は、教育県長野としては、大正時代から既にあった。 私どもの「農村医学夏季大学」構想も、もちろんそのような信州的雰囲気から生まれたことは確かといえよう。
しかし、それは昭和36年である。まさに戦後も、高度経済成長の始まらんとする時代である。 私どもは、広く国内の保健衛生の活動家である人たちが、第一線の活動の中で、非常な苦難や困惑に遭遇している現実にまず着目した。そして、地域住民の健康を守る仕事を、基本的人権と民主的精神の運動に結びつけて、その「第一線的」意義を強調する再教育・・・それこそがわが夏季大学の主なモチーフだったといえよう。
この講座の始まった頃は、確かに古い農村生活から生じた衣食住の問題が主で、特に寄生虫や「農夫症」、また、この対策としての農村生活改善運動や農民体操などが、いろいろな立場から論じられた。
しかし、第3回目あたりからは、「農薬中毒」問題が現れ、続いて変貌する農村社会と農業労働の中で、「主婦農業」「農村と社会保障」「食品添加物と洗剤の危機」等々、何れも、農村や農業における高度経済成長路線の健康破壊的ひずみが問題として取り上げられている。
昭和55年(第20回)以降になると、この講座の内容は、もっぱら老人の医療保健問題に傾いてくる。農村人口の急速な老齢化現象がその基礎にある。それも単に医療機関の立場からでなく、福祉の問題まで含めて、更にこれを地域全体の立場から「地域づくり」の一環として取り上げるようになったのである。
そして今日におよんで、「寝たきり老人」「呆け老人」のケアのための「中間施設」問題を取り上げるとともに、村の中での「ボランティア」活動を、農協組織などを通して、積極的に推進することを提唱するに至っている。
若月賞について
1992年(平成4年)元・厚生省医務局長 大谷藤郎氏の提案により、若月名誉総長の長年にわたる業績を記念し、全国の保健医療分野で「草の根」的に活動されている方を顕彰するために制定されました。毎年、夏季大学の席上で表彰式が行われています。
《選考委員》 (敬称略・五十音順)
- 井 出 孫 六 (作家)
- 行 天 良 雄 (医学博士・医事評論家)
- 樋 口 恵 子 (東京家政大学教授)
- 宮 本 憲 一 (大阪市立大学・滋賀大学 名誉教授)
これまでの受賞者(第1回~第15回)
これまでの受賞者(第1回~第15回)(363.2KB)
これまでの受賞者(第16回~第20回)
(敬称略・五十音順)
| 2007年 第16回 受賞者 |
本田 徹 (ほんだ とおる)(特定非営利活動法人 SHARE=国際保健協力市民の会・代表理事) 氏は卒後まもなくの1977年、青年海外協力隊の一員としてアフリカのチュニジアに派遣され、途上国の厳しい医療の現実に直面した。携帯した若月先生の 「村で病気とたたかう」に感動し、1979年帰国と同時に佐久総合病院に勤務した。若月先生の指導のもと4年間農村医療に従事しながら、専門臨床の面では 消化器内科の土台を築いた。1983年東京・日産玉川病院に転勤、日本国際ボランティアセンター(JVC)に出会い、この組織内に海外援助活動医療部会と してシェアを発足させた。シェアとは英語で「分かち合う」ことを意味し、それをロゴにして「市民による協力」をうたっている。最初は協力隊のOB、 OG5~6名や一般市民のボランティアでスタート。85年にエチオピアの旱魃・飢餓問題が起き、現地においてJVC・SHARE共同で1年間バラックの病 院を運営し、5万人の診療を行った。これを契機にシェアの活動を本格化させた。1988年からカンボジアで母子保健活動を開始。92年からは同国農村地域 に医師、看護師、地域保健専門家などを派遣し、郡レベルでの保健システムの構築や保健人材育成・伝統的産婆などのトレーニングに取り組んだ。90年からタ イに看護師らを派遣し、下痢予防のための保健教育、人々の健康に関する意識・生活改善などの活動を展開した。99年から東ティモールでも活動を開始し、診 療支援などの緊急救援活動、医療スタッフを派遣し地域保健活動を行い、とくに2003年以降保健教育の教材開発・保健教育普及員の養成に力を入れている。 近年はタイの東北部でHIV/AIDSとともに生きる地域づくりの活動、カンボジアにおける母子保健およびHIV/AIDS予防啓発活動、南アフリカでの HIV/AIDS陽性者支援、また国内においては在日外国人の医療相談、AIDS相談などの活動、東京・山谷地区や新宿地域などでも、医療に手の届かない ホームレスの人たちへのボランティア医療支援を行っている。 |
| 2008年 第17回 受賞者 |
藤島 一郎 (ふじしま いちろう)(浜松市リハビリテーション病院院長) 私は東大農学部卒業後、浜松医大に入り、当初脳神経外科医となった。最初の担当患者さんが脳腫瘍摘出術後、誤嚥性肺炎となったことから嚥下障害の恐ろし さを知った。当時は嚥下障害のリハビリテーションについての成書もなく全く手探りの状態から、自分なりに工夫して新たな治療法を生み出して行く作業の連続 であった。上手く行かず尊い命を失ったこと、不可能と思われた方が食べられるようになりスタッフや患者さんと共に喜びを分かち合ったこと、これらの連続で 今日を迎えている。 |
| 外口 玉子 (とぐち たまこ)(社会福祉法人かがやき会理事長) 45年前、私は保健所から精神科病院へと働く場を変えた。以来、こころ病む人たちが置かれている理不尽な状況に、同時代を生きる者としての目線を問われ、 変革への重い課題に迫られ続けてきた。この20年余りの間、制度化以前より、有志の協力を得て、精神障害者が地域で暮らし続けていくための“拠点づくり” に取り組んできている。 当事者の要請に呼応しながら、当事者もその支え手も相談できる場、安心して過ごせる居住の場、仲間との交流や生活情報を得られる場、そして働く場として、 地域の人々が集い憩う喫茶店やパン工房を立上げてきた。そのような場での当事者の主体的な動きに励まされ、共に社会へのメッセージ発信を試みてきている。 領域を越えたヨコのつながりを大事にしながら、地域づくりに向けて“多様な参加の仕方と柔軟な協働のしくみづくり”の可能性を探っている。 |
|
| 2009年 第18回 受賞者 |
湯浅 誠 (ゆあさ まこと)(NPO法人 自立生活サポートセンターもやい 事務局長) 私は、ホームレス状態にある人たちや貧困状態に追い込まれてしまった人たちを支援する活動を行っています。活動していると、よく動機やきっかけを聞かれる ことがあります。最初のころ、私は戸惑いました。ドラマチックな動機があったわけではなかったからです。しかし、徐々に「自分にそうさせたのは、どういう 背景だろうか」と客観的に自分史を眺め始めるようになりました。いくつかの「心当たり」が出てきて、それが現在の自分につながっている、と感じるように なってきています。今回は、そういう今の時点から再構成した自分史を主軸にして、私と活動の関わりを考えてみたいと思います。 |
| 村上 智彦 (むらかみ ともひこ)(医療法人財団 夕張希望の杜 理事長) 私は、北海道で薬剤師、臨床検査技師となり医療に関わってきました。その後医師となり、北海道で地域医療に従事することを目標に自治医科大学で研修し、北 海道瀬棚町で自分が描いていた地域医療を具体化しました。残念ながら市町村合併でこの夢は破れましたが、その後破綻した夕張で再び北海道の地域医療モデル 作りに挑戦することになりました。限界自治体、少子高齢化、地域間格差、医療崩壊等様々な問題の中での挑戦ですが、そんな中で得られたものも沢山ありまし た。今回の講演ではそんな経緯やこれからの目標についてご紹介したいと思います。 |
|
| 2010年 第19回 受賞者 |
池田 陽子 (いけだ ようこ)(JAあづみ・総務開発事業部福祉課) 農協の生活指導事業とは「何のために」「誰のために」「何をするのか」を常に問い続けてきたが、協同活動の主役である組合員をステージ上に招き上げ、生き活き(いきいき)と活動してもらう方法論として今に生かしてきた。 また、JAでなければできない福祉活動・福祉事業を実現するため、協同組合の原点に立ち返り、組合員・地域住民と協働して、最期まで自立して暮らし続けることのできる「あんしんの里」づくりに挑戦し続けている。 |
| 2011年 第20回 受賞者 |
飯島 裕一 (いいじま ゆういち)(信濃毎日新聞社編集委員) 1994年に始まった「信毎健康フォーラム」の企画を担当し、一般の方々を対象に、関心の高いテーマを取り上げ、講演やパネルディスカッションを通じて日常生活に役立つ健康知識を分かりやすく提供する。 また、認知症介護家族の孤立や、施設、医療、地域の現状などを追った社会面連載「笑顔のままで―認知症・長寿社会」は、2010年度日本新聞協会賞を受賞。 |
これまでの受賞者(第21回~第26回)
(敬称略・五十音順)
| 2012年 第21回 受賞者 |
スマナ・バルア (すまな ばるあ)(WHO世界ハンセン病対策プログラムチームリーダー) |
| 2013年 第22回 受賞者 |
今野 義雄 (こんの よしお)(医療法人坂上健友会 常務理事) 1990年国立療養所長寿園が廃止された後、地元住民とともに大戸地域の医療を守るため大戸診療所の開設に尽力された。 開設後も事務長として医師をはじめとしたスタッフ確保や教育を行った。 交通弱者対策として地元医師会に交渉し、自宅から診療所へのドアからドアへの送迎システムを構築し医療へのアクセスを確保した。 |
| 2014年 第23回 受賞者 |
レシャード・カレッド (れしゃーど かれっど)(静岡県島田市 レシャード医院 院長) アフガニスタンのカンダハール出身のレシャード・カレッド氏は、1969年に来日。 千葉大学を経て京都大学医学部を卒業し、87年日本に帰化された。 現在、静岡県島田市にレシャード医院、高齢者福祉施設を開設、「病んでいる人のところへ元気な医者が出向くのが当たり前」と、在宅医療や福祉に精力的に取り組んでいる。 また、故国アフガニスタンの復興に向けて2002年にNGO「カレーズの会」を立ち上げ、現地で診療所や学校を建設、難民医療・教育に献身的な支援を続けている。 人間愛あふれるその信念は、「弱いものを支えるのが人としての義務」と言い続けた若月俊一先生の魂にまさに合致している。 |
| 2015年 第24回 受賞者 |
古川 和子 (ふるかわ かずこ)(中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会 会長) 高見沢 佳秀 (たかみざわ よしひで)(元八千穂村衛生指導員) |
| 2016年 第25回 受賞者 |
旭 俊臣 (あさひ としおみ)(医療法人社団弥生会 旭神経内科リハビリテーション病院) 佐藤 元美 (さとう もとみ)(一関市病院事業管理者 国保藤沢病院 一関市参与) |
| 2017年 第26回 受賞者 |
和田 浄史 (わだ じょうじ)(川崎医療生活協同組合 川崎協同病院 外科部長) |






