診療科の特色
循環器内科や他の多職種とハートチームを形成し、患者さんのニーズにあわせた質の高い治療を行います。
従来の標準的な外科手術はもちろんですが、TAVI(経カテーテル的大動脈弁置換術)や小切開による心臓手術、大動脈瘤に対するステントグラフト治療などの低侵襲治療に取り組んでいます。
また、東京慈恵会医科大学の國原孝教授の指導のもと、大動脈弁形成術、自己弁温存大動脈基部置換術および胸腹部大動脈瘤人工血管置換術などの手術を行っています。
診療内容
弁膜症疾患
術後の高いQOL をめざして治療を行っております。僧帽弁弁膜症では多くが自己弁を修復する形成術を施行しており、内視鏡を使用した右側胸部に8cm 程度の皮膚切開で施行するMICS(Minimally invasive cardiac surgery)手術も行っております。右開胸手術は従来の胸骨正中切開と比較し、術後早期から運転などの胸骨負荷が可能となっております。弁形成術は人工弁置換術と比較し、人工弁関連の問題が起こらないことや、左室機能温存に寄与すると言われております。当科では循環器内科とともに十分な診断と検討を行い、患者さんの状態やニーズなどをもとに保存的治療も含め、治療の選択を行っていきます。
また、平成27年からは侵襲の少ない治療として高齢者の大動脈弁狭窄症患者さんに対するカテーテルを用いた大動脈弁留置術(TAVI)を開始しました。この治療法は、長野県内で行える施設が限られている治療方法ですが、従来の手術と比較し、明らかに低侵襲であり、高齢者で体力のない患者さんなどに適切な手術方法です。これまで、手術をあきらめていた患者さんにも福音となる場合がありますので、ぜひ、迷われる患者さんがいらっしゃればご紹介ください。また、大動脈弁狭窄症に対しても患者さんの状態により、右側胸部に8cm 程度の皮膚切開で施行するMICS手術も施行しております。
また、弁膜症疾患に併施しやすい心房細動併発の患者さんには心房細動に対する手術であるメイズ手術や、脳梗塞低減効果のある左心耳閉鎖術も積極的に行っております。

冠動脈疾患
主な治療方法である冠動脈バイパス術は、低侵襲と言われている人工心肺非使用心拍動下冠動脈バイパス術(OPCAB)を基本としておりますが、症例毎に検討し、特に緊急手術症例や心臓が弱っている症例では人工心肺下にも行っております。心筋梗塞合併症に対する左室形成術などの治療も積極的に行っております。
大動脈疾患
胸部、腹部ともに開胸や開腹手術を必要とせず、カテーテル的に治療を行うステントグラフト治療が主役になりつつあります。胸部では、上半身への血流を維持するため、非開胸下に頸部分枝へのバイパス術を施行後、ステントグラフト治療を行う症例も増加しています。佐久医療センターでは、これらの治療を主に施行するためのハイブリッド手術室が設置されています。もちろん、従来からの開胸・開腹手術も施行しており、患者さんの病態、ニーズに合わせた治療の選択が可能です。

末梢動脈治療
人口の高齢化、動脈硬化疾患の増加のもと、特に下肢の動脈硬化に伴う末梢動脈疾患(閉塞性動脈硬化症)は循環器治療の分野において、重要な部分になっています。この疾患も、ここ数年、カテーテル的治療の成績が向上しており、当院においても循環器内科との十分な検討のもとに、主に当科では外科的バイパス術や血管形成術を行っています。今後もカテーテル治療とのハイブリッド治療も含めて質の高い医療を行っていきます。
成人の先天性疾患
成人期の先天性心疾患は、数は少ないですが心房中隔欠損症、心室中隔欠損症などで手術が必要になる場合があります。患者さんの病態、ニーズに合わせ、右小開胸手術を行うこともあります。
- 弁膜症疾患
- 冠動脈疾患
- 大動脈疾患
- 重症心不全
- 末梢動脈・静脈疾患
- 成人の先天性心疾患
-
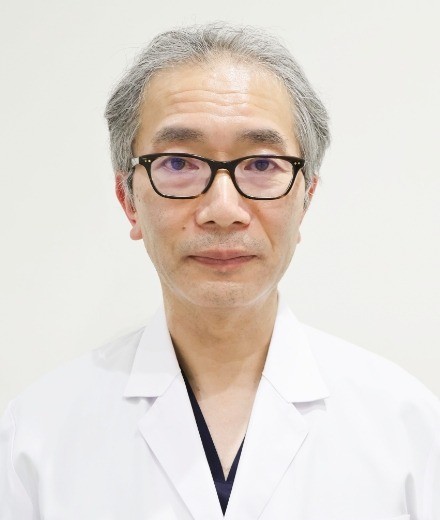
統括部長
松下 努専門分野 心臓血管外科
取得資格 日本外科学会 専門医・指導医
日本心臓血管外科学会 専門医・修練指導者
日本胸部外科学会 指導医
日本循環器学会 専門医
下肢静脈瘤血管内治療実施管理委員会 実施医
医学博士所属学会 日本外科学会
日本心臓血管外科学会
日本胸部外科学会(正会員)
日本血管外科学会
日本循環器学会
日本冠動脈外科学会 -
副部長
新津 宏和専門分野 心臓血管外科
取得資格 日本外科学会 専門医
日本心臓血管外科学会 専門医
腹部大動脈瘤ステントグラフト指導医
胸部大動脈瘤ステントグラフト指導医
経カテーテル的大動脈弁置換術(TAVR)実施医所属学会 日本外科学会
日本冠疾患学会
日本胸部外科学会
日本冠動脈外科学会
日本心臓血管外科学会
日本血管外科学会
日本人工臓器学会 -
副部長
駒津 和宜専門分野 心臓血管外科
取得資格 日本外科学会 専門医
心臓血管外科専門医
胸部ステントグラフト実施医・指導医
腹部ステントグラフト実施医・指導医
経カテーテル的大動脈弁置換術実施医・指導医
医学博士所属学会 日本外科学会
日本胸部外科学会
日本心臓血管外科学会
日本血管外科学会
日本経カテーテル心臓弁治療学会
日本救急医学会
日本集中治療医学会卒業年 卒年2002
-
医師
堀田 孟行専門分野 心臓血管外科
取得資格 日本外科学会 専門医
麻酔科標榜医
日本周術期経食道心エコー認定医(JB-POT)
腹部大動脈瘤ステントグラフト実施医
胸部大動脈瘤ステントグラフト実施医所属学会 日本外科学会
日本胸部外科学会
日本血管外科学会
日本心臓血管外科学会卒業年 2018年
-
臨床顧問
白鳥 一明専門分野 心臓血管外科
取得資格 日本外科学会 専門医
日本胸部外科学会 認定医
血管内レーザー焼灼術実施医所属学会 日本外科学会
日本胸部外科学会
日本心臓血管外科学会
日本血管外科学会
心臓血管外科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 |
松下努 白鳥一明 |
駒津和宜
(第1・2・3・5) 新津宏和
(第1・2・4・5) 松下努
(第3・4) |
交代制
(予約制) |
濱元拓
(第4) |
||
| 午後 |
|
松下努
(第1・3・4) 新津宏和
堀田孟行
(第2・4) VAD外来
|
濱元拓
(第4) |
実績
| 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|
| 外来初診患者数 | 326 | 297 |
| 新入院患者数 | 309 | 303 |
紹介時のお願い
基本的に地域医療連携室経由でのご紹介をお願いいたします。静脈瘤は本院の静脈瘤外来、下肢深部静脈血栓症は循環器内科への紹介をお願いいたします。
当科医師は信州上田医療センターで月2-3回の外来診療を行っております。信州上田医療センターの方が便利な患者さんに関しましては、信州上田医療センターにご予約のうえ、ご利用頂いても良いと考えております。
外科治療終了後、安定した患者さんは定期的CT検査や、心エコー検査などを当科、あるいは循環器科外来にて施行させていただき、通常の診療は地域の紹介元医療機関にお願いしています。循環器疾患の多くは長期間の診療が必要であり、地域での連携が不可欠です。ご協力をよろしくお願いいたします。
受診について
佐久医療センターは紹介型・
予約制の病院です。
ご本人ではなく、かかりつけ医を通じ、事前に紹介状を送ってください。
診療日
- 平日 8:30~17:00
休診日
土曜日・日曜日・祝日・年末年始













